制度環境を整備し、男性育休取得率100%を達成【三和マテリアル株式会社】
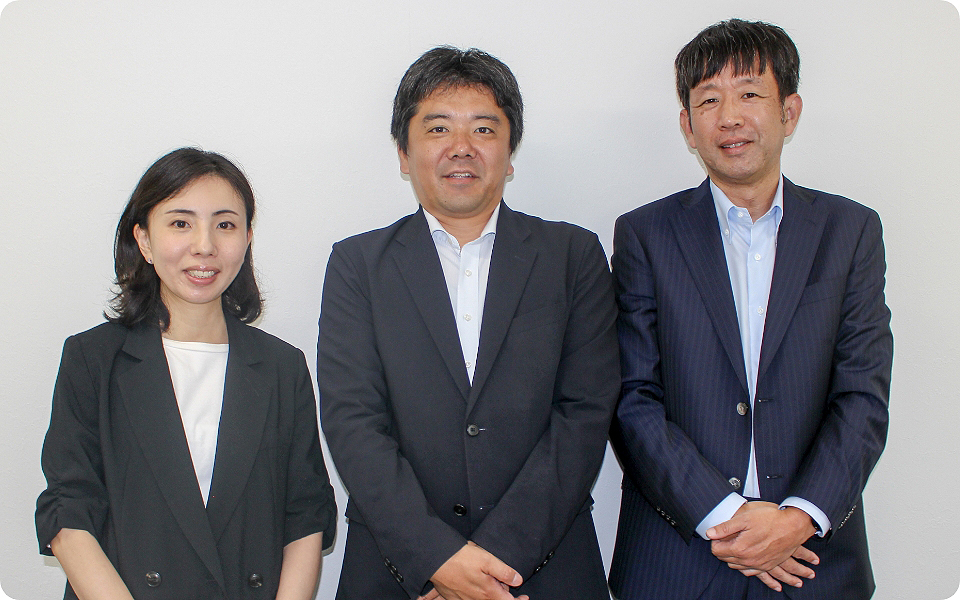
企業紹介
社名:三和マテリアル株式会社
事業内容:ファインセラミックス・非鉄金属材料・電子部品の卸売 / 従業員数:34名
代表取締役社長 岡部大輔さん
取締役 管理部長 浜中俊英さん
管理部 部長代理 経営企画担当 岡部陽子さん
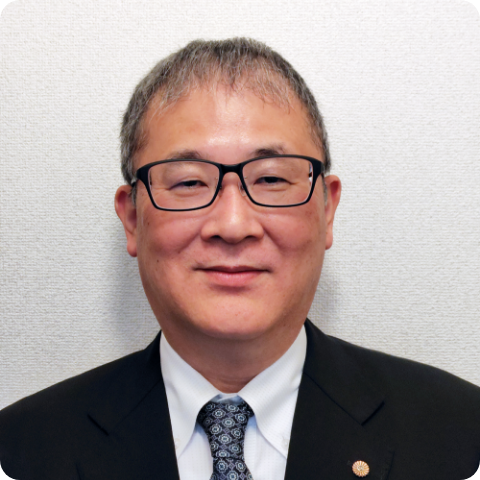
藤井 靖幸 Yasuyuki Fujii
社会保険労務士藤井事務所 代表
特定社会保険労務士
相談前の課題
- 男性社員については育休取得の前例がなく、申し出しにくい職場風土があった
- 法改正に対応した雇用契約の規程整備が必要だった
- 社員の意見や本音が見えにくく、上層部との認識にギャップがあった
制度活用のきっかけ
- 若手社員の定着を図るため、時代に合わせた働き方改革の実行が急務だった
- 幅広い年齢層の社員が働くなかで、育児介護の両立支援が重要課題となった
- 正しい現状把握を行うとともに、社員の意見を汲んだ制度改革を行いたかった
相談後の成果
- 男性育休取得率100%を達成し、取得が当たり前という社内風土を確立
- 育休取得から復帰までの明確なフローを整備し、管理職への研修も実施
- 法改正に対応した規程整備により、有期雇用の無期転換に関するリスクを回避し適切な運用を実現
- 社員が会社に意見を伝えやすくなり、職場環境が大幅に改善
経営陣の認識と従業員の考えにギャップあり
Q.事業内容と働き方改革に取り組むきっかけを教えてください。

当社は1932年創業の専門商社として、主にファインセラミックスや非鉄金属材料、電子部品の販売を手がけています。最も大きな販売先は自動車関連メーカーで、ハイブリッド車の車載部品として使われるセラミックス製品が売上の4割を占めています。
働き方改革については、2019年に就業規則の全面改定を行い、コロナ禍でテレワークとフレックス制度も導入してきました。有給休暇については、従前から取得しやすい環境が整っており、多くの社員が実際に取得していましたが、支店ごとの業務量の違いや繁忙期の影響で、取得しづらい場面も一部に見られました。また、育児や介護を支援するための制度設計が十分にできていない部分もあったり、改善の必要性を感じていました。
当社は東京の他、大阪、名古屋にも拠点があり、支店によって業務量や取引先からの要求が異なります。取引先によっては業務が多くなりがちで、各支店によってもアップデートされた働き方に対して理解度の差がありました。
Q.今回、エンゲージメントサーベイと専門家派遣を利用したのはなぜですか。
これまでも制度整備は進めてきましたが、従業員の本音や職場の実態が見えにくく、上層部との認識にギャップがあるのではと感じていました。以前に従業員へアンケートを実施した際には、有給取得の改善など率直な意見もあり、経営陣が考えている以上に課題があることが分かりました。
特に男性の育休取得については、規定はあったものの前例がない状況で、男性従業員が取得を申し出るのは難しかったようです。また、20代から60代まで幅広い年齢層の社員が働いている当社では、育児だけでなく今後、介護の問題も顕在化すると予想されます。
想定以上に厳しい意見が従業員から寄せられるのではないかという不安があったことから、エンゲージメントサーベイを実施するには躊躇もありました。しかし、働き方改革を真に推進するためには、まず現状を正確に把握し、社員の声を汲み取った改革を進める必要があると考えたのです。
専門家の知見を活かして「育休取得フロー」を整備
Q.エンゲージメントサーベイの結果はいかがでしたか。

結果は概ね良好で、ほっとした部分もあります。藤井先生と面談した際にも褒めていただきました。ただ、他の項目と比較して、スキルアップや能力開発に関する満足度がやや低い傾向にありました。
そこで社員がどのような能力開発を求めているのか、より詳細なヒアリングを実施することを藤井先生から提案を受けました。追加でアンケートを行ったところ、これまで提供していた外部研修の意図が十分に伝わっていないことや、営業スキル向上に関する研修への要望が多いことが分かりました。
Q.育児休業に関してはどのような支援を受けましたか。
育休を取得してから、復帰するまでの明確なフローを整備するためのさまざまな助言をしていただきました。制度は整備されていても、実際に活用しづらいのではあまり意味がありません。積極的に活用するには、会社側がしっかり対応できる必要もあります。
そこで従業員本人やその配偶者の妊娠について報告を受けた際は、まず「おめでとう」と祝意を伝え、その上で育休制度があることを積極的に説明する、速やかに管理部へ情報共有するといった具体的な対応手順を明文化しました。
さらに管理職向けに研修を実施し、社内説明会では男性も育休を取得できることを強調して周知しました。社長からのメッセージも含めたリーフレットを作成し、制度利用を会社として奨励していることを明確に伝えようという意志の表れです。これらの取り組みをスムーズに実行できたのも、藤井先生からお聞きした他社の実施事例など、さまざまなアドバイスあってこそだと思っています。
男性の育休取得率100%。現場の意見が環境の改善につながる
Q.改革の結果、どのような変化がありましたか。
説明会を行ってから育休に関する相談が増え、現在では男性の育休取得率は100%になっています。最初の相談者がしっかり育休を取得できたことにより、組織内に取得しやすい雰囲気が生まれ、その後も取得が続いているのだと考えています。以前のような管理職の属人的な判断のばらつきが減り、一部の支店や部署で感じられていた「休みづらい」という風潮の解消にもつながったのではないかと思います。
この他、有期雇用で嘱託社員として採用するケースでの無期転換規程の整備など、就業規則を見直す際にも具体的なアドバイスをいただきました。さらに、ハラスメント相談窓口も新たに設置しました。社内だけでなく社外窓口も設けることで、相談しやすい環境を整えることにしました。実際の相談が発生しないままでいることがベストですが、会社としてハラスメントを放置しない、容認しない姿勢を示すことにもつながっているかと思います。
Q.能力開発についてはどのような改善を図りましたか。
営業スキルの向上をはかりたいという要望が多いと分かったため、営業関連の研修メニューを充実させました。研修内容を会社が一方的に決めるのではなく、社員が希望するプログラムがあれば提案、申請できるルールがあることも改めて周知しました。以前から存在していたこの制度が十分に浸透していなかったことも明らかになり、従業員とのコミュニケーションの重要性を再認識しました。
育児から介護まで。あらゆる従業員が働きやすい職場を目指す
Q.今後の展望について教えてください。

育児支援については一定の成果を得られましたが、今後さらに重要なのは介護への対応です。育児と異なり、介護はいつ区切りを迎えるのか予測ができません。93日までと期間制限のある介護休業制度だけでは対応しきれない可能性もあるため、対象者には特別なフレックス制度の導入も検討しています。
近年は若手社員が増えており、子育て世代への支援を充実させる一方で、社員の年齢層が上がれば介護の問題も現実化してきます。老若男女、幅広い世代が働きやすい会社を目指していきたいと思います。これまでの取り組みによって、従業員の意見が反映され、職場環境が改善されているという実感を持ってもらえているようにも感じています。ぜひこの組織文化は大切に守り、育てていきたいと思います。
Q.「専門家派遣」の利用を検討中の企業へメッセージをお願いします。
働き方改革や労務管理について、中小企業が独力で対応するには限界があります。法改正への対応はもちろん、実際の運用面でも専門的な知識や他社事例を知る専門家のアドバイスは非常に貴重です。
エンゲージメントサーベイについても、客観的なデータとして現状を把握でき、具体的な改善策を検討する良いきっかけになりました。課題が見つかっても、それを改善していけば必ず職場環境は良くなります。経験豊富な専門家が自社の状況に寄り添ってアドバイスしてくれる貴重な制度を、多くの中小企業に活用していただきたいと思います。


